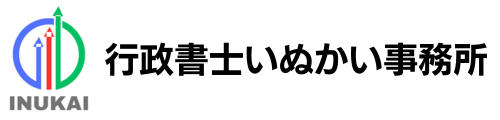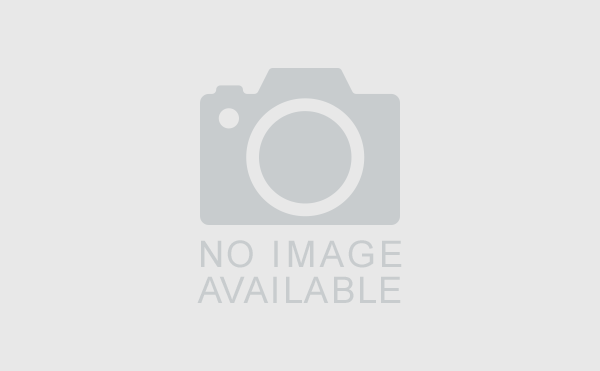酒類販売業免許の要件のキホンを解説します
酒類販売業免許の申請代理を110,000円から代行します!
酒類販売業免許に関するあなたの「むずかしい!」「めんどくさい!」を当事務所におまかせください!

酒類販売業免許の取得を考えているあなた、酒類販売業免許の申請に困っていませんか?
酒類販売業免許は要件が厳しく、また揃えなければならない書類が多いうえに、税務署の職員ともコミュニケーションを取りながら進めなければならないため、取得までの難易度が高い免許です。
この記事では、これから酒類販売業免許を取得したい人に向けて、要件についてわかりやすく解説しています。
通信販売酒類小売業免許の要件は?
酒税法第10条では、酒類販売業免許の要件について規定されています。要件を大きく分けると以下のとおりです。
- 人的要件
- 場所的要件
- 経営基礎要件
- 需給調整要件
人的要件とは?
酒税法第10条では、酒類販売業免許を受けることができない人について規定されています。一部を抜粋して記載すると以下のとおりです。
- 酒類製造免許もしくは酒類販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと
- 申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
- 国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
- 未成年者飲酒禁止法、風俗営業法等の法律、刑法又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していることと
場所的要件とは?
酒類販売業の販売場は以下の要件を満たす必要があります。
- 申請販売場が酒類の製造場、販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと
- 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従業者の有無、代金決済の独立性、その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること
通信販売を行う場合でも販売場は必要です。PCとデスクが置けるスペースだけでも構いません。
賃貸の場合はオーナーから事務所利用する旨の承諾が必要です。また、バーチャルオフィスや仕切りのないシェアオフィスなどは、販売場として原則認められません。
経営基礎要件とは?
財務諸表(個人の場合は収支決算書)からは、以下のことがチェックされます。
- 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っているか(債務超過になっていないこと)
- 最終事業年度以前3事業年度において3年連続で資本等の額の20%を超える額の欠損を生じているか
また、申請者(法人の場合は役員)が次の経歴を有しているかもチェックされます。
- お酒の販売業の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営しているか
- お酒の販売業や、調味食品等の販売業に通算して3年以上従事または経営しているか
※申請者に酒類販売の経験が無ければ「酒類販売管理研修」を受講してください。(法人の場合は役員が受講してください)
※通信販売の場合は、通信販売の経験の有無も要件とされる場合もあります。
需給調整要件とは?
- 設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人もしくは団体でないこと
- 酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと
ご自分で届出がむずかしいときは・・・
酒類販売業の免許申請は、書類に慣れていない方にとってはとても難しく感じられ、また申請書類の作成も税務署との調整もハードルが高く、とても自分で申請することは難しいと思ってしまうのではないでしょうか?
当事務所では、愛知・岐阜・三重を中心に「酒類販売業免許代行サービス」を110,000円(税込)からご提供しています。申請に関するご相談はもちろんのこと、あなたの「めんどくさい!」「むずかしい!」を、ぜひ専門家である当事務所にお気軽にお聞かせください!
事務所概要

行政経験豊富な当事務所にお任せください!
当事務所は愛知・岐阜・三重を中心に許認可申請を主に取り扱っています。特に、税務署に申請する「酒類販売業免許」については、地元である愛知県を中心に多くのご相談やご依頼をいただいております。
「酒類販売業免許」の一番のハードルは税務署とのコミュニケーションです。通常、私たちが税務署の職員とお話しすることはあまりありません。ですので、なんとなく税務署に怖いイメージを持っている方もいるのではないでしょうか?
酒類販売業免許においても、取得については一定の要件がもちろんありますが、事業者様によって状況は異なります。免許を申請する事業者様の状況を踏まえ、いかに免許が取得できるように税務署の担当職員とコミュニケーションを行うか、そこが専門家としての腕の見せどころです。
また、約15年間の市役所勤務経験から、書類の作成や税務署とのやり取りも迅速かつ正確に行うことができます。初めてのご相談はまずLINEから。ぜひお気軽にお問い合せください!
| 事務所名 | 行政書士いぬかい事務所 |
| 代表者 | 犬飼慎一 |
| 事務所所在地 | 〒491-0859一宮市本町3丁目9番10号ラフォーレデュオ403 |
| 保有資格 | ・行政書士(愛知県行政書士会所属、登録番号第24190392号) ・宅地建物取引士 |
| 代表者プロフィール | ・昭和55年愛知県あま市生まれ ・京都大学卒業後、一宮市役所入職 ・退職後、2024年3月行政書士いぬかい事務所設立 |
よくあるご質問
-
自分が経営する飲食店で酒類を提供したいと考えていますが、酒類の販売業免許は必要ですか?
-
飲食店で酒類を販売するのに販売業免許は必要ありません。しかし、例えばテイクアウト用など、その営業場以外の場所で飲用に供されるための酒類を販売する場合には、販売場ごとに販売業免許を受ける必要があります。
-
フリマサイトやネットオークションで酒類を出品したいのですが、酒類の販売業免許は必要ですか?
-
フリマサイトやインターネットオークション等のような形態であっても、継続して酒類を出品し販売を行う場合には酒類の販売業に該当し、販売業免許が必要となります。ただし、自宅で不要になったものを売るなど、継続性が認められなければ、販売業免許は不要です。
-
酒類販売業免許に有効期限はあるのですか?
-
酒類販売業免許に有効期限はありませんので、一度取得すれば更新不要です。
-
酒類販売業免許は申請から何日くらいで取得できますか?
-
提出書類に不備が無い場合、申請から2ヶ月程度です。
-
酒類販売業免許を受けずに酒類販売業を営んだとき、罰則はありますか?
-
酒類販売業免許を受けずに酒類販売業を営んだときは、酒税法第56条の規定により、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることがあります。
お問い合わせ
LINE【365日24時間受付中】

お問い合わせフォーム【365日24時間受付中】
当事務所の業務エリア:愛知県、岐阜県、三重県